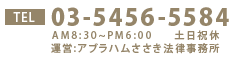契約書の押印の種類
1.訂正印
契約書の記載に手書きで二重線を引いて、手書きで修正したような場合に用います。
※修正液等を使う事はできません。
例えば、「3」を「12」に直した場合、「1字削除、2字加入」と書き加えて、その書き加えた部分に取引当事者が押印を行います。
※ここでの押印は、署名押印又は記名押印で用いたものと同じ印鑑を使用します。
※漢数字を使用すると「一二三」について改ざんが容易なため、一般に算用数字を用いることが多いです。
あまりに大きな変更になる場合、新たに契約書を作り直す、別に覚書等を作成することが一般です。
2.捨印
捨印は契約書余白に押印で用いた印鑑を押すことです。
事後の修正にある程度までは同意する趣旨で行われます。
※ある程度とは、明らかな誤字等がこれに含まれます。
但し、これを悪用すれば訂正印としてみえる外観ができるため、こと契約書においては捨印は慎重に行う方が良いでしょう。
3.割印
契約書の枚数が複数枚に渡る場合、一定の場所に記名押印・署名押印で用いた印鑑を押します。
これは、複数枚全体が一体であることを示すために行います。
袋綴じであれば表裏2箇所、そうでなければ各頁のつなぎ目に行います。
袋綴じの場合、厳密には表か裏かどちらかで足りるが慣習的に裏表両方行うことが多いので、無用なトラブルを防ぐ為にも両面に行うべきです。
4.消印
一定の条件を満たす契約書には、印紙税を納めなければなりません。
具体的には、契約書に印紙を貼り、その印紙と被るように消印を行います。
ここでの消印に使う印鑑は、記名押印・署名押印に用いた印章である必要はありません。それどころか、文書の作成人の印章でなくても良く、作成者の代理人・使用人・その他従業員のそれで足ります(印紙税法施行令第5条)。また、厳密には印章でなくとも署名でも良いです(同条)。
したがって、消印は、「作成者・代理人・使用人・従業員」の、「印章・署名」であれば可能です。
ここでの印章は、一般的な印判によらずとも、氏名を表示した日付印・ゴム印のようなものでも構いません(印紙税法基本通達第64条)。
加えて、契約当事者双方が消印しなくとも、一方のみで足ります(同条)。