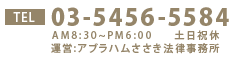文言の解釈の方法
契約書の文言の代表的な解釈の方法には、次の方法があります(厳密には論理解釈にはもっと種類があります)。
1.文理解釈
2.論理解釈
2-1.拡大解釈
2-2.縮小解釈
2-3.類推解釈
2-4.反対解釈
例をあげます。一休さんのとんち話で、けものの皮は叩かれるというものをご存知でしょうか。
ある囲碁が好きな隠居が毎晩やってくるので一休さんは眠れません。そこで、そのご隠居がけものの皮で出来た袖無しを着ていることを利用して、「けものの皮入るべからず」という張り紙をしました。ご隠居はそれにも関わらず入ってきたので一休さんが尋ねると、寺の中の太鼓も皮で出来ているので自分も大丈夫だと言いました。それに対し一休さんは、だから太鼓は棒でいつも叩かれているんですと返して、ご隠居を追っ払ったというお話です。
かなり長くなりましたが本論です。「けものの皮」という文言について考えてみます。
1.文理解釈では、「文字通りけものの皮」のみが含まれます。したがって、ご隠居は一旦家に戻り布でできた袖無しに着替えてから入る事ができます。
2-1.拡大解釈では、けもの以外の皮、例えば「人間の皮」(怖いですね…)も含まれることになりえます。ご隠居は入れません。
2-2.縮小解釈では、「そのご隠居のいつも着ている皮で出来た袖無し」のみが含まれることになりえます。ご隠居は着替えて入れます。また、「今まさに剥いだばかりのけものの生皮」のみをさすと考えれば、ご隠居はそのまま入れます。
2-3.類推解釈では、その規定をそのご隠居を寺に入れないという趣旨とすれば、「そのご隠居」にも適用されることになります。ご隠居は入れません。
2-4.反対解釈では、「純粋にけものの皮」のみが含まれる事になります。ご隠居は着替えて入れます。
ここでは、ご隠居は縮小解釈、一休さんはそれ以外の解釈をしたということがわかります。
以上、同じ文言であっても、解釈の違いによりご隠居が寺に入れたり入れなかったりするわけです。
すなわち、契約書の文言に争いが生じた場合には、お互いに自分に有利な解釈をして相手方に主張することになります。ここでお互いにどちらの解釈がより妥当かについて決着がつかない場合、裁判官に決めてもらうことになります。
そこでこのような紛争を予防するために、事前に契約書の文言を解釈の余地がないほどに限定しておくことが重要となってきます。