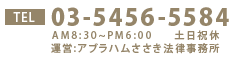契約書の文言の訂正方法
契約書の文言の訂正方法には、次の二通りがあります。
以下、5行目の「1」を「23」に訂正する場合を考えます。
1.直接法
「1」に二重線を引き、丸括弧を加えて、二重線に訂正印を押します。さらに、近くに「23」を加えます。
訂正印は契約書の押印に用いたものを使います。
2.間接法
「1」に二重線を引き、近くに「23」を加えます。
さらに、契約書の余白(一般的には上部)に「5行目1字抹消2字加入」と書き加えて、隣に訂正印を押します。
ここで、訂正箇所がその頁で一箇所しか無い場合は、「1字抹消2字加入」のみでも構いませんが、後の無用な争いを避けるために行の指定まで入れておくとよいでしょう。
それでは、直接法、間接法の使い分けはどのようにすべきでしょうか。
直接法のメリットは、間接法に比べて簡単であることです。そこで、一箇所のみの訂正であれば直接法を用いて、それ以外の場合には間接法を用いるといった使い分けが考えられます。
しかし、直接法のデメリットとして、偽造が容易であるという点があります。今回の例では、「23」に訂正し訂正印を押した後に、契約当事者の一方が勝手に「23」の後ろに「4」を書き加えると、あたかも「234」に変更したかのような外観が作出できてしまいます。もちろん実際には、契約書を二通当事者双方が保存するのが通例ですので、裁判で「234」の記載変更が当然に認められるとは限りません。一方の契約書は「23」他方は「234」となっていますから、少なくとも争いになります。また実行者等は、有印私文書偽造又は変造、及び同行使罪(刑法159条、161条)に問われる可能性があります。いずれにしても、このような無用な争いを避けるためには、間接法を用いる方が無難だといえます。
なお、間接法の「1字抹消2字加入」の数字も、「一字抹消二字加入」としてはいけません。「一」を「三」等に変更することが容易であるからです。